こんにちは!
子どものみかたブログへようこそ。
前回は、2歳児前半の主な発達から保育の内容を考えました。
▶︎【参考】2歳児前半の主な発達と保育のねらい
https://komaranaisekaiforkids.net/2025/06/24/2saizenhan-omonahattatu/
今回はその続きとして、「認知の発達」に焦点を当てながら、子どもの姿を見つめつつ、そこからどのような保育内容が考えられるかを掘り下げてみたいと思います!
その上で一緒に考えてみてくださいね。
◆ 2歳児前半の認知発達の特徴とは?
この時期の子どもたちは、一見まだまだ幼く見えるかもしれませんが、実は思っている以上に「考える力」が育ち始めています。
具体的にはこんな姿が見られます。
-
モデル(他者)と自分を区別し、まねることで自分のものとして遊びに取り入れる
-
2次元的な区別や配分を理解しはじめる
-
「どっちが多い・少ない?」がわかるようになる
-
丸や四角など、形の違いがわかってくる
-
指先で押す・引く・ねじるなど、素材を変化させるようになる
-
道具の使い方と素材との関係を理解する
-
線や円などを模倣して描くようになる
-
「1・2」などの数を覚えて言える
-
絵本の絵や写真への関心が高まる
こうして見ると、思考力や観察力、手先の操作など、認知の力が多方面でぐんぐん育っていますね!
◆ 認知の発達をふまえた保育内容のヒント
では、これらの発達を踏まえて、保育ではどんな関わりや環境づくりができるでしょうか?
① モデルと自分の区別・模倣の力
▶︎ 保育内容例:
大人が遊びの「モデル」となり、積み木や粘土などで遊ぶ姿を見せることで、子どもたちはそれを真似し、自分の遊びとして楽しむようになります。
★ポイント:
子どもが真似たくなるような魅力的な遊び方を大人が工夫し、「やってみたい」を引き出しましょう。
② 区別・配分・同意の力
▶︎ 保育内容例:
色や形の違う素材を使って、並べたり分けたりする遊びを取り入れます。ままごとや人形遊びで「これ誰の?」「どっちにする?」といったやりとりも◎。
★ポイント:
子どもが考える時間を大切にしながら、同意や確認を求めてきた時はしっかりリアクション!小さな納得の積み重ねが大事です。
③ 多い・少ないの理解
▶︎ 保育内容例:
素材を配ったり、分けっこしたりする中で、「こっちはたくさんあるね」「少ないね」などの言葉がけで数量感覚を育てます。
★ポイント:
「自分の分を多くとっちゃう」姿も大切な学びの過程です。叱るより「気づかせる」関わりを意識してみましょう。
④ 形の区別と選択
▶︎ 保育内容例:
丸・三角・四角など基本の形を使った積み木遊びや、見立て遊びを展開。形に名前をつけて遊ぶことも◎。
★ポイント:
大人がモデルとなって「これは四角だね」など、ことばと形を結びつける支援を。
⑤ 指先で素材を変える操作の力
▶︎ 保育内容例:
粘土やひも通し、キャップの開け閉めなど、指先を使って素材を動かす遊びをたくさん用意しましょう。
★ポイント:
「やってみたい!」を引き出す環境づくりがカギ。道具の使い方も段階的に。
⑥ 道具と素材の関係理解
▶︎ 保育内容例:
スコップやカップで砂や水をすくう、移すなどの操作遊びを通して、「道具を使う面白さ」を感じられるようにします。
★ポイント:
身の回りの自然素材(葉っぱ・小枝など)も取り入れると、より豊かな体験に。
⑦ 描画:線や円を描く模倣
▶︎ 保育内容例:
お絵描きでは、横・縦の線、円などの模倣を取り入れた遊びが楽しくなる時期です。
★ポイント:
大人が書いたものを真似する姿が多くなります。良いモデルになる準備を♪
▶︎【参考】書くことの発達について
https://komaranaisekaiforkids.net/2023/01/11/hoikunonerai-kakutikara/
⑧ 2つの数を覚えて言える
▶︎ 保育内容例:
「1・2」「トントン・パッ!」など、リズムや掛け声と一緒に、数に親しめるようにします。
★ポイント:
音として「覚えて言える」段階ですので、まずは楽しみながら、同じ数を配るなどの経験を積ませましょう。
⑨ 絵本や写真への関心
▶︎ 保育内容例:
読み聞かせの後に絵について尋ねたり、「これは誰?」と本人や先生、保護者などの写真を使ってのやりとりを楽しんだりします。
★ポイント:
子どもが「知ってる!」「わかった!」と感じられるような関わりが、認知の育ちをさらに後押しします。
◆ まとめ:考えることが面白い!を引き出す保育へ
2歳児前半の認知発達は、「見る・聞く・まねる・やってみる」の繰り返しの中で、どんどん豊かになっていきます。
2次元的な理解が深まることで、種類・量・形など、1つの物事にも多様な側面があることに気づいていく時期です。
自分で選び、試して、納得する——
そんな主体的な活動を、ぜひ大人の関わりや環境構成で引き出していきたいですね!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。
もし皆さんの現場で「こんな保育、子どもが面白がってました!」という実践例がありましたら、コメントやメッセージで教えていただけるととても嬉しいです♪
子どもたちの育ちを、私たち大人の視点と関わりで豊かにしていきましょう!
🌱関連リンク
✅次回予告
次回は、2歳児前半に見られる「運動の発達」について掘り下げてみようと思います!


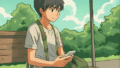
ご意見・ご感想など 子どものみかたブログ読者の方から頂きましたご意見などです。