こんにちは。
子どものみかたブログにようこそ!
今回は、「今の若い子たちの人間関係」から、これからの保育に必要なことを考えてみたいと思います。
■ つながることが前提の時代
最近の若い子たちは、当たり前のようにスマホを持ち、SNSを通じて友だちとつながっています。でも、その「つながり」は、選べるものではなく、前提になっているようにも感じます。
「つながらない」という選択肢が許されない空気。
ちょっとした人間関係のトラブルが、一気に周囲に広がってしまう。
冗談すら言いにくく、誰かに見られているような感覚。
それって、すごく息苦しいことじゃないかなって思いますよね。
■ “共感”の会話が増えている背景
若者の会話を聞いていると、「〜だよね」「〜じゃない?」といった、同調を求める表現が多い気がします。
自分の意見を断言するより、相手に合わせる。
否定をしない。
距離感にとても敏感。
少しでも“違う”ことを言えば、弾かれてしまうかもしれない——。
そんな不安があるのかもしれません。
■ 情報はある。でも、行動には移しにくい
スマホで調べれば、何でもすぐに分かる時代です。
そのぶん、「やってみる前に調べて、できなさそうと判断してしまう」ことも増えたように感じます。
情報はあっても、経験は不足している。
だからこそ、冒険しにくい・リスクを避ける傾向があるのかもしれません。
でも同時に、裏の情報や社会の問題点など、かつて見えかった“現実”にも目を向けていて、ある意味すごく冷静で、鋭い。
時には屁理屈に思えるところもあるけれど、しっかりしているところもある。
これって、希望でもあるなと思います。
■ では、保育にできることって?
そんな時代を生きる子どもたちに対して、保育で大切にしたいのは、
「違ってもいい」と思える空間をつくること
だと思います。
それは今に始まったことではないかもしれません。
でも、今の若い世代の繊細さや孤独感を見ていると、より意識的に「自分らしくいていいよ」と伝えていく必要を感じます。
■ すべての子どもが“自分の人生”を歩けるように
誰もが自分らしく、自分の人生を生きるためには、人との違いを知り、受け入れ合うことが土台になります。
それは、保育の現場で、小さな子どもたちが「違うって面白い」「みんなちがって、みんないい」と感じる経験の積み重ねから育まれていくものです。
今の若い子たちの姿から見えてくる課題。
そこに目を向けることで、これからの保育がより良く、柔軟な、個々にとっての意味のあるものになっていく気がします。
まとめ
- 今の若者は、つながりに縛られているような人間関係に悩んでいる
- 同調が前提で、自分を出しにくい時代
- 保育では「違ってもいい」から「違って当たり前」という安心感を育てることが大切
- 異なる価値観に触れ、目から鱗を落としたり、認め合う経験が、自分らしさを育てる
最後に
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
今を生きる若者の姿から、私たち大人が学べることもたくさんあります。
これからも、子どもたちの“自分らしさ”を支える保育を、一緒に考えていけたら嬉しいです。


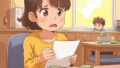
ご意見・ご感想など 子どものみかたブログ読者の方から頂きましたご意見などです。