こんにちは、「子どものみかたブログ」です。
少年法の改正は「少年法の適用年齢を18歳未満に引き下げるべきだ」という声が強まり、2022年4月1日に民法改正による成人年齢の引き下げに合わせて行われました。これにより、18歳と19歳の少年は「特定少年」として、従来の未成年とは異なる扱いを受けることになりました。
確かに、少年による重大な事件が報道されると、厳罰を求める声が大きくなりやすいものです。
でも、果たしてそれだけでいいのでしょうか?
私たち保育者や教育者は、もっと別の視点からこの問題を考えるべきだと思うのです。
子どもを簡単に悪者にしない視点を持ちたい
どんな子どもにも子どもである限り「成長の可能性」があります。
今、たとえ問題があったとしても、それは「成長の途中」であると見なすことが、保育や教育の根本姿勢です。
もし重大な犯罪を起こしてしまった子がいたとき、その背景にはどんな育ちがあったのか、家庭や学校、社会はどんな関わりをしていたのか。
そうしたことを丁寧に振り返ることが、大人の責任ではないでしょうか。
それを子どもに(子どもではなくなるが)罪を押し付けることだけで締めくくられ、大人の振り返りや反省が行われないことが懸念されます。
つまり、子どもの育つ環境が改善されないまま、存続することになってしまいます。
子どもが罪を犯した時、社会はどう向き合う?
たとえば、ある少年が凶悪な事件を起こしたとしても、
「この子は悪い子だった」で終わらせてはいけないと思うのです。
児童福祉や教育が、すべての子どもにとって本当に機能していたのか?
そこに改善すべき点はなかったか?
社会全体で、冷静に、かつ真剣に問い直す必要があります。
子どもが悪かったのではなく、
「大人側がもっとできたことがあるのでは?」という視点を忘れてしまうと、
同じような問題はまた繰り返されてしまうのではないでしょうか。
「更生」や「矯正」に目を向けると、、
厳しい罰を与えることで犯罪を防ごうという考えは、確かにわかりやすいです。
でも本当に大事なのは、「今後再び起きない」道筋をつくること。
子ども時代に「モンスター」とされてしまった子には、それまでの過程で気付くことが出来なかった大人(社会全体)の過ちとして、その後の人生で最低限立ち直れるチャンスを与える必要はあると私は思っています。
それでも困難なケースには、社会を守るために柔軟に対応し、期間を限定しない継続的な矯正・更生支援の仕組みも、今後もっと検討されてよいのではないでしょうか。
子どもの支援者としては、、
「少年法があることで、罪が軽くなると子どもが思っている」
そんな声もよく聞きます。
でも、そのような思考にならないように育てるのが、私たち大人の責任なのではないでしょうか。
本当に大切なことは何なのか。
私たち保育者や教育者が、子どもの可能性を信じて、
そして保育・教育そのものの力も信じて、
よりよい社会のあり方を目指して改善を重ねていく。
その地道な努力こそが、
子どもを守り、社会全体の安全と幸せにつながると私は信じています。
他の人はともかく、子どもの支援者が諦めたら、その時点で何もかも終わってしまいます。
おわりに
被害者やその家族への支援は、もちろん大前提です!
それは絶対に欠かせませんし、今よりももっと、そして負った心の傷によっては、生涯公的にも支援していく必要があるのかもしれません。
でもそれと同時に、加害者となってしまった子どもたちがどうしてそうなったのか、
その背景を知り、社会が受け止めて改善する姿勢を持つことも、
未来の子どもたちを守るためには欠かせない視点ではないでしょうか。
子どもが単に「悪者」と決められる前に、
大人が社会が変わる必要がないのか。
そんな思いを持って、保育者としてこれからも子どもを支援していきたいと思います。

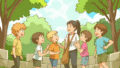

ご意見・ご感想など 子どものみかたブログ読者の方から頂きましたご意見などです。