こんにちは。
いつも「子どものみかたブログ」を読んでくださってありがとうございます!
前回は学童の来所と降所について考えてみましたが、今回は自由遊びそれも部屋での自由遊びについて考えてみたいと思います!
部屋遊びの内容
学童でする部屋遊びというのは、どのようなものがあるでしょうか?
主なものだけを挙げますと、、
などでしょうか。
では、それぞれの遊びを少し考えてみましょう。
ブロック系
ブロック系の遊びと言っても、今や様々にありますよね。
私があえておすすめするとすると、レゴブロックなどで遊ぶ際に、大き目の基盤の板を用意することでしょうか。基盤板があることで、何もない状態から何かを作る時のハードルがグッと下がります。
よくブロックで遊ぶ際に、何を作ったらいいかわからないという声をよく聴きます。それで説明書通りに作るという子どもも居ます。それももちろん楽しくて、色んな成長発達に貢献するでしょうが、イメージをさらに広げようとする時には、基盤板があると便利です。
カード系
トランプやウノなどは、支援者が個々の力を把握するということがとても重要な遊びではないでしょうか。ですので、後ほど学年別に自由遊びを考えてみたいと思います。
あえておすすめしたいのは、今や様々なものが売られていますが、社会性をテーマにしたカードゲームでしょうか。
カルタ系
カルタもとても盛り上がる遊びです。ですが、これも苦手だったりして楽しめない子どもが居たりしますので、注意が必要です。
ここで、特に百人一首について少し考えてみたいと思います。
百人一首について
学童で特に百人一首に力を入れているところって、割とあるのではないでしょうか?
私は百人一首を一律に学童で取り組むことは、ちょっと注意が必要だと思っています。
その理由は、、
などが考えられます。
そもそも百人一首は飛鳥時代から鎌倉時代辺りまでの歌人によって詠まれたものです。それを学校教育では、小学校でも高学年になってから学ぶことが多いようです。学校との整合性が取れないことも、少し考えた方が良いのかもしれません。
詠まれている内容も、恋愛であったり生活であったり、身近に感じるのがまだ難しいものです。身近に感じることが出来ないものは、子どもにとって意欲や興味を持ちにくいですので、無理にもしくは嫌々取り組むということになりやすくなります。
もし、学童で一律に取り組む際は、子どもが興味を持って意欲的に取り組めているのかに注意しながら取り組む必要があるでしょうね。坊主めくりは学童でもとても盛り上がる遊びですので、まずは坊主めくりで百人一首に親しんでおく、その間に内容にも興味が持てるように支援するということは有効かもしれません。
カルタ系もカード系の遊びと同じように、社会性やコミュニケーションのねらいを盛り込んだものがありますので、お勧めです。
パズル系
パズル系の遊びは記憶や集中力、図形の構成力を養います。絵柄が興味のある物だと特に集中しやすくなります。ですので、パズルの絵については、出来るだけその時に流行っているものや興味が持てるものを幅広く選ぶとよいのではないでしょうか。
野球盤など
野球盤なども一部の子どもたちには大人気です。ですが、感情的になってヒートアップしやすいですし、大切に遊ばないと壊れてしまうこともあります。また、野球のおもちゃですとルール自体が難しいですので、最初は大人が介入した方が良い場合もあります。
乱暴に扱うと壊れてしまうようなおもちゃで遊ぶ場合は、子ども同士で上手に遊べるようにするためのルール化がとても大切ではないでしょうか。
ままごと系
ままごと系は主に女児に人気の遊びです。ですが、支援者としてはジェンダーは意識しすぎないように子どもたちには支援したいです。
家族の役割を決めてごっこ遊びをしたり、お店屋さんを運営するために協働をし、役割分担をしたりして、社会性を養うことが出来ます。ままごと遊びも支援者の介入によって、よりまとまりのある目的意識のあるものにも出来ますので、腕の見せ所です。
将棋など
将棋などは、特に頭を使う戦略的な遊びが好きな子どもに人気です。
ご家庭で楽しんでいると、とても強い子どもが居たりしますね。そのような少し強い子どもが居ると、学童の子ども相手では物足りなく感じている子どもも居るのではないでしょうか。そのような子どものためには、支援者が相手が出来るといいですが、なかなか時間の確保が難しいのが悩ましいですね。それに3年生辺りに強い子が多く、来所時間が遅めでおやつや宿題などで忙しくて時間が無いこともあります。
オセロについては将棋よりもハードルが低くて親しみやすいですので、ぜひ用意しておきたいです。あと、将棋で山崩しをするのもとても人気の遊び方です。音が鳴った鳴っていないでもめるのも定番です。
また、将棋で思い出しましたが、ひよこまわり(回り将棋などの言い方もある)は将棋よりもハードルが低く、特におすすめの遊びです。
読書系
宿題や読書の時間を設けている学童もあると思いますが、それは別途考えるとしまして、ここでは自由遊びとしての読書を考えたいと思います。
活字離れが言われる昨今ですが、活字から情報を得るというのはまだまだ貴重で有効なことなのかもしれません。というのは、アニメや映画、今では動画もそうかもしれませんが、原作の小説などの方が面白く感じたというのはよく聴くことです。そう、活字の情報というのは想像力を掻き立てるのです。特に子どもの頃は映像に頼らず、頭の中で想像を膨らませて楽しむという経験は今後の生き方にも影響しそうに思えます。
とはいえ、今の映像技術というのはひょっとしたら頭の中での想像を超えているものもあるのかもしれません。原作を超えた映像。凄いですよね、今の映像化のテクノロジーって。でも、単純に映像に頼って情報を取り入れてばかりですと、想像などこれまでの頭を使う作業が省かれて脳の発達にも影響しないのでしょうか?
根拠はありませんが、、
また、特に活字から情報を得るのが好きな子どもも中には居ます。そういう子どもにとって、興味関心が持てる本がたくさん用意されているというのは、その子どもの将来を左右するくらいのことなのかもしれません。
本を読むことで私がお勧めなのは、本を読むのが特に苦手な子どもも居ますので、子どもに定期的にアンケートを取り『どんな本が読みたい?』か聞き、それに応じた本を用意するということです。興味関心がある本というのは、活字が苦手な子でも意欲がわくものです。あと、保護者が子どもに特に活字を読ませたいとご相談を受けた場合は、ゲームの説明書を一緒に楽しみながら読むことをお勧めしたりしていました。余談ですが笑
漫画についての考え方ですが、私は学童という場ではアリだと思っています。今、漫画でわかる歴史や科学、自然などの本が山のように存在します。それで漫画はNGとしてしまいますと、とてももったいないことですよね。活字ばかりじゃしんどく感じるけど、絵があると興味が持てるって子どもには割とよくあることです。
あと、いわゆる少年誌などに掲載されている漫画をどう扱うかですが、それも自由遊びの時間ならアリではないかと思います。内容は選ぶでしょうが、基本的には子ども向けと言われる漫画なら何でもいいのかなと思っています。人が亡くなるなどの残酷な描写がある作品については、色んな考え方があるでしょうが、私は支援者が一緒に読んだり、時には作品について説明するなどして、残酷であることの意味を補足することで、デメリットを無くしていくことが可能だと思っています。(ちなみに発達的には現実と架空の世界の区別がつき始めるのは4歳頃と言われています。個人差があるので注意が必要ですが。)
小学校低学年で読むと楽しくて有効な作品があれば、ぜひ教えて頂けたらと思います!
プラレールやピタゴラスイッチ系
プラレールなどについては、ある程度のスペースの確保が必要になります。ですので、広い部屋がある学童に限られます。複数で協力しながら、とてもダイナミックな遊び方が出来ますので、出来るといいのですが、どこでもというわけにはいかないでしょうね。
将棋の藤井聡太さんが子どもの頃遊んでいたと言われているおもちゃキュボロが有名ですが、これらの遊びも子どもの発想や思考を深めるのに有効ではないかと思います。
お絵描き系
お絵描きも大好きな子どもが居ます。
そのために、白い紙や画材は準備しておきたいところです。
白い紙は、全て用意するとお金もかかりますので、保護者にご協力頂き、仕事などで裏が白のコピー用紙で余っているものを頂けたら嬉しいですね。
保護者との連携の機会もあえて作ってしまうのもよいのではないでしょうか。
ペンなどを使うために、机に写らないように下敷き用の広告などの紙も必要です。
塗り絵についても、出来るだけ個々の子どもの興味関心に合うものを印刷して用意出来ると良いと思います。
そのためにも、PCや印刷機は必須だと思いますが、導入されていない学童もまだまだあるようです。
学童でも子どものために印刷機くらいは使えた方がいいと思うのですが、国や地域行政の方、よろしくお願いいたします。
1年生の遊び
1年生だけに室内での自由遊びを考えますと、1年生は一番早く来所してきます。時間的には、平日は13時30分辺りになりますでしょうか。ですので、他の学年に邪魔されず苦笑、伸び伸び遊べる時間があるということになります。
ですが、1年生というのは発達的にはまだ三次元可逆の形成期に入ったばかりで、まだまだ大人の支援が必要な時期と考えられます。学童という枠組みの中で、子どもたちだけで上手に遊ぶというのはちょっと難しい場合があります。ですので支援者が介入して、今後子ども同士で上手に遊べるようにサポートすることが大切になります。(国や地域行政の方には、ぜひそのための保育体制を考えて頂けたらと思います。)
遊びも、先ほど挙げましたようなおもちゃで始めは一番わかりやすくて、簡単な遊び方をすると良いのではないでしょうか。そういう意味では、社会性の発達だけではなく、1年生の認知力についての基本的な知識を持った上で、学校の先生から情報を頂くなどして個々の力も把握しておく必要があります。
2年生の遊び
2年生になりますと、少し遅めに帰ってくる日が出てきます。
発達的には、友達に興味が出てきて協力したり、反面自己主張が出来るようになってきて、友達とぶつかることも増えてきます。そのような時に支援者としてうまく仲介をして相手の気持ちに気付き、今後の成長につなげることが大切な時期です。
自己知覚が進み、落ち込むこともありますので、上手にフォローして自信や意欲を失わないようにサポートしたいです。今後のために、いい意味で友達とぶつかることがとても有効な時期とも言えます。
自由遊びについては、認知力、運動能力、社会性の発達から、徐々に発展して行ける時期です。
3年生以上の遊び
3年生になりますと、来所時間が遅くなり、おやつ中であったりすることもあります。
何か取り組もうとすると、早い来所日を選んでするということになります。
過ごす時間が限られていて、学校で疲れていることもしばしばありますので、様子をチェックすることは重要です。
学校で何かあったりすると、明らかに不機嫌だったりします苦笑
ですので、室内での自由遊びは限られた時間がほとんどですが、高度な遊び方が可能になりますので、その要望には出来る限り応えられるように準備しておきたいです。
室内での遊び方は、流石3年生と言いますか、自ら発展的に遊ぶ姿が見られ、支援者としては安全面の見守りが中心で良い場合が増えます。ですが、特定の友達が来所しない、辞めてしまったなどで、孤立して過ごしている子どもも出てきます。そういう子どものために、支援者が話し相手になったり、役割を与えたり、興味が持てる本や工作などを準備しておくというのも有効ではないでしょうか。
発達的には仲間意識が強くなり、ギャングエイジと言われるように大人に反発したい時期です。ですが、理屈が通った説明や説得は有効で、よく大人の話を聞こうとする時期でもありますので、時間がかかることもありますが、しっかりと向き合ってコミュニケーションを取りたい時期でもあります。
そう考えますと、1年生から3年生で全く手がかからない時期というのは無いんですよね。
3年生以上については、基本的には3年生の支援方法を応用することでいいかなと思います。
まとめ
いかがだったでしょうか?
1年生は遊び方自体も支援する必要がありますし、3年生は3年生で高度な遊びや社会性を支援する必要がありますので、支援者は絶対的に不足していますよね。
おもちゃに関しましては、子どものタイプも違いますし、どれが良いとは一概に言えないところがありますが、海外製のカードゲームやおもちゃにもとても良いものがありますので、よかったら探してみてください。
学童での室内での自由遊びで、良い過ごし方があれば、ご意見お待ちしています!
では次回、第3回学童を考えよう! 自由遊び屋外編でお会いしましょう!
それまでお元気で。

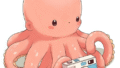
ご意見・ご感想など 子どものみかたブログ読者の方から頂きましたご意見などです。