こんにちは。
いつも「子どものみかたブログ」を読んでくださってありがとうございます!
前回の第0回導入編に続いて、今回から実践に入り「学童保育所における来所と降所」について考えてみたいと思います。
…と、その前に。
そもそも「学童に来ること」って、みなさんはなんて呼んでいますか?笑
学童に来ることをなんという?
「登所」でしょうか。「来所」? 「登園」なんて言い方も、時々聞きますよね。
学童を「○○園」と呼んでいたり、保育園やこども園と併設されていたりすると、「登園」のほうがしっくりくる場合もあるかもしれません。
学童保育所の呼び名は?
また、学童保育所自体の呼び方も、いろいろあります。
昔は「留守家庭児童室」「放課後児童クラブ」「放課後児童室」なんて呼ばれていたり、地域によっては「なかよし学童」といった愛称で呼ばれることも。
でも、子どもたちや保護者の間では、やっぱり「学童」という呼び方が一番定着しているように思います。
その中で、ちょっと気になるのが「なかよし学童」という名前。
もちろん、温かみがあって親しみやすい名前ではあるのですが、私はこの「なかよし」という言葉に、少し違和感を覚えることがあります。
なぜなら、「なかよしであること」が前提のように感じてしまうからです。
たしかに、最終的には「相手を思いやる」「集団の中で協力する」といったことは育っていってほしい力です。でも、小学校低学年の子どもたちにとっては、まだ他人を尊重したり、我慢したり、協調したりすることがまだ育ちの過程であって、難しい場合がある発達段階でもあります。
それなのに、「なかよし学童」という名前があることで、
「仲良くしなきゃいけない」
「みんなと一緒にいられないとダメ」
そんな大人からの“無言のプレッシャー”を子どもが感じてしまうこともあるのではないでしょうか。
中には、人と関わることが苦手だったり、集団にいるだけでしんどさを感じている子もいます。そんな子にとって、「なかよしであること」を求められる場所は、安心できる居場所ではなくなってしまうかもしれません。
それに、大人だって「みんなと仲良くする」ことがいつもできているわけではないですよね?
「仲良くしなさい」って言いながら、大人同士がギスギスしていたりする現実もあります。
だからこそ私は、もっと子どもの“そのまま”を受けとめられるような、
子ども主体の居場所としての学童を感じられるネーミングがいいなぁ…と思っています。
最近は、「インクルーシブ」や「多様性」への意識の広がりもあって、「なかよし学童」という名前は少しずつ減ってきているようですが、まだまだ多く残っているのも事実です。
単に仲が良いということではなくて、色んな人が居ていい場所。相手を尊重し、自分を尊重される場所。そんな場所から学べることがあるという。
もちろん、名前だけでその学童の良し悪しが決まるわけではありません。
でも、「名前」には、その場所の“メッセージ”が込められていると思うのです。
子どもたちにとって、『ただいま!』といつも素直に言えて「帰ってきたくなる放課後の居場所」の入り口となるような、温かくて自由な名前。
みなさんだったら、どんな名前がいいと思いますか?
学童にやってきたら…
ちょっと話が逸れてしまいましたが…(汗)今回は、子どもたちが学童保育所(以下、学童)にやってきたときの流れや、帰るときのことについて考えてみたいと思います。
🌟まずは「ただいま!」からスタート
子どもが学童に帰ってきたら、まずはランドセルや荷物を自分のロッカーにしまって、先生に連絡帳を渡す…というのが多くの学童での基本的な流れではないでしょうか?
(水筒だけはすぐ取り出せるように、別のかごに入れる工夫をしているところもありますよね)
🧺ロッカー事情って実は大事
学童では、制作物や着替えなど荷物も多くなるため、ある程度の大きさのロッカーが必要です。多くのところで、名前シールが貼られていて、子どもが自分の場所を覚えやすく工夫されています。
配置についても、兄弟姉妹、仲の良い子同士、あるいは学年のバランスなど、トラブルを避けるための配慮がされていることが多いと思います。ロッカー前って、実はけっこうトラブルが起きやすい場所だったりしますからね…。
📒悩ましい「連絡帳」事情
連絡帳の扱いも、学童によってさまざまです。
紙のノートを使っているところもあれば、メールやLINEでやり取りしているところもあります。
個人的には、出欠管理や伝達がラクになるLINEのようなツールに統一できるといいなと思っているのですが、まだまだICT化が進んでいない学童も多いのが現状です。
紙の連絡帳を使う場合は、A5より少し小さめのノートや、手作りカバーをつけているところもありますね。確認ミスを防ぐために、サインやハンコで出欠を記録したり、体調などは直接書き込んだりと、それぞれ工夫されているのではないでしょうか。
ただし、どうしても出し忘れや渡し忘れってありますよね…。
そういったことも考えると、やっぱりLINEのような一括管理ツールの方が便利だなと感じます。
出欠の確認って、実は学童の業務の中でもかなりの負担になる部分です。
登録人数が多い学童では、出欠確認だけで終わってしまうなんてことも。連絡がないままの欠席が続くと、万が一の事故につながることもあり得ます。だからこそ、保護者や学校のご理解・ご協力がとても大切なんですよね。
🚪降所の流れもそれぞれ
帰る時間(降所)についても、学童によっていろんなスタイルがあります。
・一人で帰る子と、お迎えの子に分かれている
・17時など決まった時間に一斉に帰るグループがある
・他のクラスと合同になる時間帯がある
などなど。保護者の働き方や地域の事情によっても異なるでしょう。
降所の際には、お迎え時間の確認や忘れ物チェック、子どもの体調などの引継ぎが必要です。実は来所よりもシンプルに見えて、結構気を遣う場面でもあります。
少し注意が必要なのは「本当にお迎えの人が保護者か関係者かどうか」の確認。
いつもと違う人が来る場合は、「今日はおばあちゃんがお迎えに行きます」といった連絡が必要だったり、子どもの関係者であることを証明できるカードを発行している学童もあるようです。
また、日が短くなる季節は、帰る時間を早めたりする学童も。
子どもたちの安全を守るためにも、社会全体で「暗くなる前にお迎えに行ける」環境が整うといいなと感じています。
🕔夕方の時間の過ごし方も大切
子どもが少なくなる夕方の時間帯に、普段できないような遊び(卓球、メンコ、コマなど)を楽しめるように工夫しているところもあると聞きます。
でも、どんなに子どもが減っても、保育は必要だと私は思います。
その時間に事務作業や掃除などを始めることもありますが、子どもたちの様子を見ながら、子どもを第一に考えて行うことが大切ではないでしょうか。
✉ まとめ:学童での来所・降所、どうしてる?
今回は、学童に「来たとき」と「帰るとき」について、現場目線で色々とお話させていただきました。
地域や学童ごとにやり方は違うかもしれません。
「うちではこうしてるよ!」「こんな工夫がうまくいってます」など、コメントやメッセージで教えていただけたらとても嬉しいです☺
次回は第2回、「自由部屋遊び」についてです。
またお会いできるのを楽しみにしています!

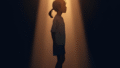

ご意見・ご感想など 子どものみかたブログ読者の方から頂きましたご意見などです。