こんにちは☺ いつも子どものみかたブログをお読みいただき、ありがとうございます!
今回は、男性保育士の生きる道!と題しまして、男性保育士が保育現場で活躍するために必要なことを私なりにアレコレ考えてみたいと思います。
ですので、基本的には男性保育士以外の方は対象としていませんが、男性保育士がどのような立場や意識を持っているのかを知ってもらう機会になればという想いもなくはない苦笑ですので、もしよろしければ男性以外の方も、お付き合いください。
保育現場は言うまでもなく、ほぼ女性の職場と言ってもいいです。
それは、単に女性が多いという意味だけではなく、保育という仕事が男性よりも女性の方が得意!ということもあります。
そんな保育現場で、男性として保育現場で上手くやっていくには、何が必要なのでしょうか?
まずは、保育現場というのは男性にとってどのような現場なのか、見ていきたいと思います。
男性にとっての保育現場とは?!
保育士の男女別割合
保育士の男女別割合は、令和2年の厚生労働省の保育士登録者数等によると男性保育士は全体の約5%となっています。 また幼稚園教諭の男性割合は令和3年の学校基本調査結果から全体の6.6%となっています。
児童養護施設や児童発達支援センターで働く男性の保育士は、保育所よりもかなり多くなっていますが、保育所では一人もいないということもあります。
また、児童福祉施設とは違いますが、学童クラブも男性の支援者が多めです!
ですので、保育の仕事がしたい男性の方で、同性が居る安心感が必要と考える方は、保育所以外の保育施設で働く方が良いかもしれません。
私は、性別に拘らない考え方が大事という前提はありますが、保育においては偏ることはあまりよくないと思っています。
支援者に求められることを考えましても、子どもの人権を守る視点からは、同性による支援が必要な場合や場面があります。
例えば、入所施設では自意識が強くなり、繊細さのある思春期児童も支援しますし、保育所でも自意識が芽生えてくる後期になればなるほど、トイレや着替えのような場面では、出来るだけ同性による支援が望ましいでしょう。
男性保育士の待遇
保育士の待遇は、厚生労働省の令和4年の調査によると、保育士の平均給料月額は約26万6,800円という結果でした。
また、保育士の給料を男女別でみた結果は、わずかですが男性保育士の方が、平均月収・平均年収ともに高い傾向が見られます。
男性保育士 月収27万7900円 年収404万3000円
女性保育士 月収26万6100円 年収390万5500円
また、全業種の平均は、
| 全職種 | 34万100円 | 496万5,700円 |
|---|
年収では、他の業種と比べても90万円から100万円の差があり、生活をしていく上では将来設計などを考えても、厳しいと言えます。
家庭を持ち、どうしても自分が中心になって家族を支えたい!と考える方は、選びにくい職業ということになります。
ですので、男性保育士が家庭を持つためには、共働きは必須になります。
資産があり、元々裕福な人は別ですが。
内閣府の「男女共同参画白書 令和4年版」(2022年)によると、働く夫と専業主婦の世帯は減少し続けていますが、共働き世帯は増加中です。 2001年から2021年までで約1.5倍増加しており、世帯全体の約7割にまで達しています。
他には、基本的には子どもの直接支援をすることからは離れることになりますが、多くの収入を得るために、園長になるという方法もあります。
園長になるためには、通常10年程度の保育経験が必要と言われたりしますが、私立の場合は比較的新しく設置された保育現場だったり、人材不足のため、ハードルが低いかもしれません。
しかし、運営全体に目を配る必要があり、責任の重さは公立でも私立でも変わりません。
園長の仕事は、事務処理能力だけではなく、労務管理や保育士の人間関係の調整、そして何かあったら前に出て保護者に説明をしたり、子育て支援など、それなりの経験とスキルが求められます。保育士や保護者から信頼される、人柄も必要でしょう。また、関係機関や行政との連絡や連携、会議への参加も求められますし、地域への貢献のため、場合によっては休日にイベントに参加することも求められたりして、イメージよりもかなり多忙です。
告知
〈はじめまして。 子どもの発達と保育と生きる力です!!このアカウントの目的は、4つあります。〉
・見るだけで、子どもの発達の理解が深まる動画です。
・発達を理解することで、不適切な保育を防ぎ、子ども主体の保育が可能になります。
・保育現場の課題や現状を発信して、問題の解決を考えます。
・子育ての参考にしていただける内容でもあります。
保育現場での男性保育士の評価
保育現場での男性保育士の評価は、とても厳しいものです苦笑
というのは、女性が男性を評価する時、仕事はある程度出来て当たり前!ということがあるようです。
ですので、そのような見られ方から、男性保育士が一度『使えない』と判断されてしまうと、とても厳しい評価をされることになります。
昔、先輩の男性保育者に『男は女性の2倍3倍働いて、1人前くらいだよ!』と言われたことがありますが、私なりにこの背景について考えると、
男性は、外で狩りをしたり、収穫をしたり、収入を得て帰ってくるもので、それが出来ないと生活が成り立たない、自分や我が子の命や健康が脅かされるという危機感が、本能的にあるのではないかなと感じます。
だから、身近に働く男性に対しては、どうしても厳しめの評価になるのではないでしょうか。
私が元々使えなったからという可能性ももちろんありますが苦笑、同僚の男性保育者と話していても、だいたい意見は合致します。
それに、女性は母性からか、子どもをとにかく守りたい!という強い信念があり、繊細に丁寧に子どもを観察しようとします。
それは男性保育士には、経験を積んだりかなり意識しないと、とても難しいことです!
おそらく、世の父親もそうなのではないでしょうか。
このような特技を持つ女性は、保育士という仕事にピッタリですし、男性からするとリスペクトするべき部分です。
もちろん、全員ではありませんが、男性は基本的には大雑把といいますか、何とかなるとか大丈夫でしょ!という、子どもに対して楽観的な見方をしがちです。
そういう男性保育士の意識が、女性から見て受け入れ難いということもあるのかもしれません。
ですので、男性保育士としては、子どもに対して楽観的な先入観を捨て、保育士として求められる自分になりきる必要もあるかもしれません。
男性保育士の優位性を活かすには?!
そんな厳しい女性保育士の評価がある中で、男性保育士の優位性を活かすには、女性の苦手な部分を積極的に引き受けることです!
私が考えた、男性保育士の優位性を活かす方法は、
というようなことです。
この中には、当然女性も得意な方が居ると思いますが、その場合は力を合わせて協力して仕事が出来るのではないでしょうか。
これらのポイントは、積極的にというところです。
具体的には、私の場合は、清掃などでの高所の作業や荷物の運搬、棚などの移動や組み立て、プール準備などの力仕事、そして、蜂退治や猛暑の中での草むしりなどまで、積極的にしました。
中には、それらを雑用と嫌がる保育士の方が居ますが、私はそれは違うかなと思っています。
優しかったり気を遣うあまり、消極的になってしまうと、男性保育士が保育現場で評価されることは難しくなってしまいます。
難しいタイプの子どもの支援というのは、それなりの知識やスキルが必要になりますので、専門書などで事前によく勉強しておくとよいでしょう。
DIYやパソコンのスキルも、同様です。
あとは、少し余談になりますが、男性保育士は、最初はどうしても保育士としてよりも、良くも悪くも異性として評価されるということがあります。
男性ばかりの職場でもそのようなことが起きますが、保育所は女性がほとんどの職場ですので、それがあまりに気になる人は、少し難しく感じることがあるかもしれません。
私の場合は、気にならなかったというか、気にする余裕が無かったというか、それがハードルになることはありませんでした。子どもや保護者と関係性を築くことや、仕事を覚えることがまず最優先!と思っていましたので、それ以外にはあまり意識が向かなかったということがあります。
異性として評価されることについては、あえて鈍感で居る方がいい場合もあるかもしれません。
長く保育の仕事をしていると、中には仲良くさせていただいた方も居ますが、最初の内はある程度仕事と線を引くことは大事なのかもしれません。
あとは、これも余談ですが、保護者の方との関係性にも注意した方がいいと思います。
というのは、子育て支援をしていく中では、色んなお話をさせていただきますので、稀にですが好意を持たれるようなこともあります。しかし、あくまでも支援者ですので、ある程度の距離は保つようにしないと、今後の保育や支援が難しくなります。これは男女に関わらず、言えることだと思います。
また、対応が難しいタイプの保護者は、男性保育士が対応することで有効に働くことがありますので、子育て支援のスキルを上げることも、保育現場で男性保育士が生き残る一つの方法です。
告知
〈放課後等デイサービス 40のあるあるマガジン 2か所放デイの立ち上げから関わった経験がございます!起業を考えられている方、保護者の方の事業所選びの参考に、また放デイで働かれている管理者、スタッフの方、働くのを考えられている保育士の方に、有益になる情報です! ご購入頂きますと、300円でひとり親貧困家庭の支援が出来ます😊 (ご購入頂いた売り上げは、全てひとり親家庭支援団体に寄付させて頂きます。)〉

子どもにとって、どっちがいい?!
それでは、子どもにとってどちらがいいのかというと、どちらとも言えない部分があります。
先ほども申しましたが、男性から見ると女性は保育が元々得意な、リスペクトするべき性質があります。
しかし、子どもへの想いが強すぎたり、守ろうとするあまりに感情的になったり、行き過ぎることがあります。それが、不適切な保育に繋がることがあります。もちろん、常に冷静に自己調整が出来るタイプの女性保育士も居ますし、個人差はあります。
それに対して男性保育士は、子どもに対してとてもソフトな関わり方をする人がとても多いです。それを上手く活かせると、子どもの安心感に繋がったり、伸び伸びと自分の力を発揮させることが可能になります。
だからと言って、男性保育士ばかりになると、その甘さから、怪我人が続出するでしょう苦笑
また、保育のスキルが一定のレベルにないと、保育もまとまりのないものになるかもしれません。子どもの命を守るためには、時には厳しさも必要ですが、それが過度にならないように注意が必要です。
子どもは温室では育ちません!
なので、女性的な見方と男性的な見方が、バランスよくあることが、子どもにとってとても有益なことではないでしょうか。
告知
〈子どもが困らない世界 ここま 子どもたちがさまざまな状況で困っている時、支援の手助けとなる方法を一堂に集めたサイトです。困り感を抱えている子どもたちや、発達の凸凹などのある子どもたちの保育に焦点を当て、参考になる情報を提供しています。〉
小児性愛者について
以前に、男性ベビーシッターが小児性愛者だったということで、事件になりました。
最近でも、園児に繰り返し性的暴行を加えていた保育士が逮捕される事件がありました。

それがきっかけで、男性シッターが登録できなくなったりして、働けなくなりました。
でも、ちょっとこれは行き過ぎだと私は思っています。
ベビーシッターの仕事に関わらずですが、不適切な関わりをする可能性は、女性も男性もあります。
また、小児性愛者は、男女含めて人口の5%程度居ると言われています。
そして、あえて子どもに関わる仕事を選んでいますので、保育現場ではその割合は高くなります。
〈参考〉
ならば、男女関わらず不適切な関わりをする保育者を排除したり、チェック出来ればいいのではないかと思います。
以前から、シッターのスキルや内容はどのようにチェックされるのかが気になっていましたが、シッターの活動中は男女に関わらず録画をすることを推奨すべきだと思うのです。
録画をすることで、ベビーシッターは活動内容をチェックされますし、怪我など問題のある関わりをされた疑いがあれば、録画を見直すことが出来ます。
よく、昔の外国映画なんかで乱暴なシッターが、赤ちゃんを雑に扱うシーンが出てきて、笑いになったりしますよね苦笑
ああいうのを避けないとって思うのです。
放デイを含めて、保育現場で虐待が起きてしまう原因は、知識や技術のないこともありますが、同時に人の目がないことが大きな要因だと考えられます。
なので、私が働いていた時にも思っていたのですが、子どもの入所施設等では特に1対1対応が増える、夜間は録画をすることを必須にしないと、弱い立場の子どもの人権は守れないと思っています。
子どもの意志やプライバシーとの兼ね合いがありますが、長い目で見た子どもの人生の方が大切ではないでしょうか。
大人は録画されていたら保育しにくい!とか言われますが、それは自信やスキルがないことや後ろめたいことがあるのが要因ではないかと思います。
男性女性に関わらず、子どもがまだ幼い間は、1対1対応の場面は録画する!ということが一般的になれば、余計な疑いも晴れます。
保育士同士の信頼が基本ではありますが、弱い立場の子どもを守ることを優先するということでよいのではないでしょうか。
また、保育現場は出来るだけオープンにして、人の目に触れるようにすることも有効です。
それが虐待や不適切な保育も防ぐことになります。
以上が、私が男性だけをシッターや保育士にしない!ことよりも、もっと子どものために有益だと思えることです。
まとめ
今回は、「男性保育士の生きる道!」というテーマで、男性保育士が保育現場で活躍するために必要なことをお話ししました。
男性保育士は、女性が多い保育現場でどうやって上手くやっていくのかをあらかじめ考えておくことで、スムーズに適応することが出来ます。
現実的には、男性保育士の割合は全体の約5%に過ぎず、家庭を持つためには共働きが必須であることや、待遇の問題から30歳を前に退職する男性保育士が多いのが現状です。
しかし、男性保育士としての優位性を活かすことで、より良い保育を提供することができます。そのためには、女性の苦手な部分を積極的に引き受けることが重要です。また、保護者との関係性を築くことや、子育て支援のスキルを上げることも大切です。
保育現場では、男性的なものと女性的なものの考え方のバランスが取れた環境が、子どもにとって有益です。
男性保育士としての役割を理解し、その優位性を活かすことで保育現場で活躍し、子どもたちにとって、より良い育ちのための環境を提供できるでしょう!
最後まで、【子ども主体の保育への道!】番外編 男性保育士の生きる道!をお読みいただき、誠にありがとうございました。
もし、ご意見ご感想などございましたら、コメントで頂けますととても嬉しい限りです。
〈【子ども主体の保育への道!】子ども主体の保育のための10の講義〉
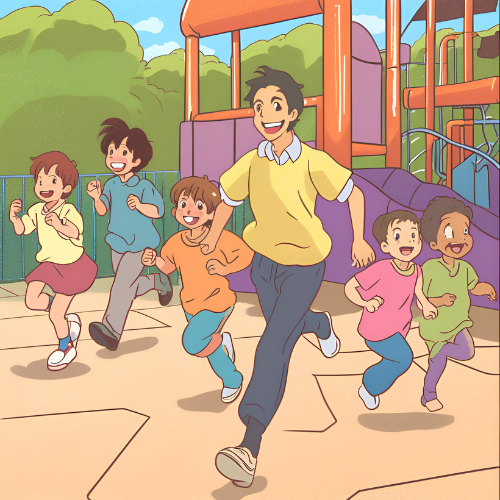


ご意見・ご感想など 子どものみかたブログ読者の方から頂きましたご意見などです。