こんにちは。
「子どものみかたブログ」です!
今回は、この度京都府宇治市の保育所で起きた食事場面での保育士による虐待事件を受けて、保育士として日々直面する「子どもと食事」のことについて、少しじっくり考えてみたいと思います。
リンク
なんで食べてくれないの〜?
私たち大人が作るお弁当や給食。
子どもたちには、できれば全部きれいに食べてほしい!そう思う方も多いはずです。
保護者の方や給食室の栄養士さんが、子どもの健康や成長を願って、あれこれ考えて準備してくれた大切な食事。
だからこそ、残さず食べてほしいって思ってしまうんですよね。
でも、現実はというと…
「いらない〜!おしまいー!…それでさぁ、昨日ね〜」
なんて言いながら、まったく手が進まない(笑)
なぜ?って思いますよね苦笑
「食べない」にも、いろんな理由がある
子どもが食べない理由って、実はたくさんあったりします。
-
そもそもお腹がすいていない
-
好きな食材じゃない
-
食べること自体にまだ興味が持てない
-
味覚がまだ完成していない
-
感覚過敏or鈍麻
-
食べ物が異質なものに感じられる(初見の食材とか)
食経験がまだ浅い子にとって、給食の中には「え?これ食べれるの??」っていうレベルのものもあるんです。
子どもによっては食材なのに味がしないので「消しゴム食べてる感じ」であると言われたりします。
味覚については、就学後になってからようやく定着していくと言われています。
「全部食べる」が目的になると…
「残さず食べてほしい」という気持ちが強すぎると、
ついつい無理やり食べさせようとしてしまうことも…。
でも、それって一定の子どもにとってはすごくつらいことです。
とくに味覚が未定着な子どもや食感に敏感な子など、偏食がある子には逆効果でしかありません。
私が見たケースでは、学校から帰ってきた後もまだ給食をモグモグしていた子もいました。
それはもう…さすがに見過ごせない状況で、学校にお話ししたこともあります。
食べるって、楽しいことにしていける?!
子どもにとっては食べるということも初体験です!
なので、食べることについても第一印象が大切になります。
ですので、保育士としてはまずは
が大切なんだと思います。
例えば、、
-
食事の導入にパペットや紙芝居を使ってみる
-
先生や友達と一緒に「おいしいね」って言い合える雰囲気をつくる
-
無理なく、挑戦する意欲が持てるようにする
-
挑戦して少しでも食べられたときは、思いきり褒める!
こうした日々の積み重ねが、子どもの「食べる力」を育てていくんですよね。
一人ひとりに合わせた「食」の支援を
もちろん、集団での食事には時間やルールも必要です。
でも、その中でもできることはたくさんあります。
-
食材の大きさや形、調理方法などを変えてみる
-
量を調整して「全部食べられた!」という達成感を味わってもらう
-
スプーンなどを持たせてみるなど、少し手伝ってみる
-
家庭での食の様子を保護者と共有し、無理のないペースを考える
-
食事の延長は本人の意思の確認をした上で、時間を区切って終わりにする
-
気が散りやすい場合は、つい立てを使用する
時間の設定は、余裕を持たせることが大切です。
そのために、支援者の人手が必要になりますがスタートと終わりを長めに取り、一斉ではなく、その間に食べたらOK!という方法もあります。
完食できなかったことが「できなかった自分」となってダメージを与えないように、ほどよく区切りをつけることも大切です。
長い目で見てあげたい「食の育ち」
子どもが本当に「食」に興味を持ち、楽しく食べられるようになるには、時間がかかるものです。
だからこそ、保育の現場では「今、全部食べること」よりも、
「将来、食べられるようになること」を大切にしていきたいですね。
まとめ
食べることは、子どもの健康と発達に欠かせない大事な営みです。
でもそれは、楽しいものであってこそ育っていくものです。
「食べるっていい!」「楽しい!」「みんなと一緒だとさらにいい!」
そんな気持ちが少しずつ育っていけば、子どもたちはきっと、自然にいろんなものを食べられるようになっていきます。
あせらず、比べず、でも諦めずに。
子どもと一緒に「食」の世界を広げていける保育を大切にしていきたいですね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
共感していただけるところがありましたら、とても嬉しいです!
関連記事
乳幼児に完食の指導は必要か?!


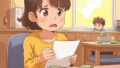

ご意見・ご感想など 子どものみかたブログ読者の方から頂きましたご意見などです。