こんにちは☺ いつも子どものみかたブログをお読みいただき、ありがとうございます!
今回は、私が最近ある病気で入院した際に、感じたことを率直に書いてみようと思います。
私は、ここ十数年は、入退院を繰り返している状況で、その合間に保育の仕事をしている感じなのですが、今回の入院は最初の入院とは明らかに違いがありました。
入院するきっかけは、これは明確なのですが、保育業界ではありがちな、仕事で無理をしたからです!
そんな状況が3年ほど続き、今となってはどうしようもないのですが、無理をしたことについては、かなり後悔をしています。
ですので、保育現場で働いている皆さんには、無理をしないで!と言いたいですね。
若いうちは体も元気で無理が効いてしまい、気づきにくいのですが、疲労は蓄積され、20年近くなってくると、必ず体のどこかしらに異変が起きます。
ですので、しんどいな、疲れているなと感じたら、遠慮なく休むようにしてください。
保育者に何かあったら仕事に穴が空くというのは、保育者の問題ではなく、本来運営側の危機管理の問題ですので、何を言われても気にしないでもいいのです。
前置きが長くなってしまいましたが汗、この度の私の入院生活をみていきましょう!
かなり驚いた最初の病棟看護の様子
当時、私が入院した病院は、公立系の大き目の病院なのですが、看護師をたくさん配置していることで有名な病院でした。
毎日、10人程度の看護師が、入れ代わり立ち代わり私の看護に当たって頂きました☺
大げさではなく。
10日から2週間程度の入院だったのですが、毎日知らない看護師の方と対面するという感じでした。
しかも、それは病気の程度によるものではなく、入院患者は皆、そんな感じだったと思われます。
なぜそれがわかるのかというと、一日のスケジュールでわかります。
私のベッドにやってくる看護師の看護の内容というと、、
これらの仕事が、全員違う看護師だったりしました。
これら以外に、看護師以外の方のサービス業者の仕事内容としては、、
がありました。
まだまだ他にも日常の患者からの要望に応えるということもあります。
例えば、爪切りの用意や髪を洗う、入浴介助などなど、無数にあります。
『一体、1つの病棟に何人看護師が居るの?!』と聞いてみたところ『だいたい15人くらいかな。私も把握していないんです』って笑
日勤の看護師の方は、必要に応じてトイレの介助や急患の看護もありますし、手術や入退院の準備作業もあります。
日中は、患者の直接看護をメインにする担当と、その周辺の仕事を補助する担当に分かれているようで、看護体制的には、とても充実している印象でした。
それが最初の頃の入院の看護の様子でした。
今回の看護の様子
では、今回の入院の様子はどうだったのかというと、、
おしぼりやお茶の配布は業者がすることになっていました。
また、食事の配膳もほぼ業者の仕事になっていました。
これは正直とても残念に思いました。
そして、ベッド周りの衛生管理も業者の仕事になっていました。
コロナの影響もあるのかもしれませんが、病院運営のためにはとても合理的で、看護師を雇う費用も少なくなるでしょうし、多岐に渡る看護業務の負担軽減にもなるでしょう。
しかし、とても大事なものと引き換えになっている気がしました。
合理的なことよりも大事なこと
私は専門家ではないので、詳しくはわかりませんが、看護は周辺の仕事と一体になっているように思います。
患者と顔を合わせる機会が多いほど、看護師は病状を細かく把握することになりますし、患者の精神的な不安の軽減にもなります。
今回の入院で『私は看護師ではないので、わかりません。看護師に聴いてください!』と業者の方にハッキリ言われている患者さんがいました。
そうなるよね、、って。
そのような返し方をされること自体が、様々な不安を抱えている患者にとってはしんどいんですよね。
私は、看護の事はよくわかりませんが、患者にとって病状も顔も知っている看護師に病状についてはもちろんのこと、それ以外にも世間話も出来るということほど、精神的な薬は無いと思うのです。
業者の方がやることは看護ではなく、あくまでも作業です!その作業を看護師がやることで看護になるのではないでしょうか。同じことでも。
最初の入院では、看護師の方と少しでも病気以外の話も出来ることで私自身、気が紛れ、入院中の不安やストレスがかなり軽減されていたと思います。
今回の入院での患者さんたちの様子を見ても、最初の頃と比べても落ち着かない方がとても増えたようにも感じました。
それがよけいに看護師の負担になっていないかな?!って思えるくらいに。
告知
〈放課後等デイサービス 40のあるあるマガジン 2か所放デイの立ち上げから関わった経験がございます!起業を考えられている方、保護者の方の事業所選びの参考に、また放デイで働かれている管理者、スタッフの方、働くのを考えられている保育士の方に、有益になる情報です! ご購入頂きますと、300円でひとり親貧困家庭の支援が出来ます😊 (ご購入頂いた売り上げは、全てひとり親家庭支援団体に寄付させて頂きます。)〉

必要な看護と理想の看護師の体制は?!
何度目かの入院で、夜間のお茶の配布は無くなっていました。
それは夜勤の体制上も大変そうですし、仕方ないかなって思っていましたが、今回はかなりの違いを感じました。
看護師の負担軽減も大切だと思います。それは保育現場で身に染みて理解していますので、そうなのですが、それならば業務を一部だけでも良いので元に戻してほしいなって思いました。
例えば、ベッド周りの衛生管理ですが、知らない人にベッド周りを触られるというのはちょっと違和感があります。病室には日用品もアレコレおいていますし、プライベートの一部も見られることになりますし、せめてこの作業は看護に戻してほしいなって。
お茶、おしぼり、給食の配膳は業者の方にお願いをして、他は出来るだけ看護師の顔が見られる機会を作って頂けたら嬉しいなって思いました。
ベッドに居て、安静にしておかないといけない患者は、孤独で仕事や家族、将来など、何かといらないことを考えてしまったりするものなんですよね。それに、思うように動けないストレスも半端なくて。
もちろん、ナースコールはありますので、それでいいのでは?!という意見もあるとは思いますが、なかなかボタンを押すのって勇気がいるし、話し相手をしてほしいために呼ぶのもどうかと思いますし、そういうことでもないんですよね、、苦笑
医療業界は優遇されている?!
これもよく言われることですが、国の支持団体になっているせいか、医療業界はやや優遇されているようです。
コロナ対策費の件をとっても言われたことですが、コロナ期間に病院設備がかなり良くなったことはあちこちで見られます。
〈コロナ予備費12兆円 使途9割追えず〉

コロナ患者のための病床は増えない代わりに、備品や医療機器が更新されたり、Wi-Fiを導入したりされた病院が増えました。また、使い道が幅広過ぎて、自治体が何に使っても良いように思えるような制度になっていました。
Wi-Fiの導入は、長期の入院になるととても有難いものですが、後に、コロナのための病床は増えなかったけど、病院の預金口座の残高が増えただけと指摘する調査もありました。
お金を使うなら、看護体制の充実や患者の利益のために使って欲しいですね。
〈参考:コロナ対応で、ひどい扱いを受ける保育現場〉

看護師は凄い!
これは何度入院しても思うことなのですが、看護師は凄い!!ってことです。
よくこんな大変な仕事を引き受けてくれているなあって。
看護師の仕事は3Kと言われたりしますが、
お腹が痛くなりそう、、苦笑
私が入院していた時にも、深夜に隣に患者さんが運ばれてきて、重い手術の直後だったようで、一晩中看護に当たっていました。
いろいろ大変そうな患者さんにも、眉1つ動かさずに献身的に対応されていて、凄いです。
実際には、私が入院した病院は、看護師の回転が早く、毎回知らない看護師が何人も居るということにはなっていましたが、それだけ心身を削りながらしないといけない仕事なのでしょう。
印象に残っている看護師の方はたくさん居るのですが、1番は最初の手術直前に私が不安になっていると、自分の看護学生時代の失敗談を話して落ち着かせようとしてくれた方が居て、それは一生忘れられないだろうなって思います。
たくさんの看護師の方々に、たくさんの温かいお気持ちを頂き、感謝してもしきれないくらいです。
告知
〈はじめまして。 子どもの発達と保育と生きる力です!!このアカウントの目的は、4つあります。〉
・見るだけで、子どもの発達の理解が深まる動画です。
・発達を理解することで、不適切な保育を防ぎ、子ども主体の保育が可能になります。
・保育現場の課題や現状を発信して、問題の解決を考えます。
・子育ての参考にしていただける内容でもあります。
看護師と保育士の共通点
看護師と保育士、どちらも精神労働や感情労働であるということは共通していますね。
感情労働とは、、
医学的な知識も必要ですし、何かしらの病を抱えている人の看護ということで、保育士よりも難易度が高いでしょうし、高度な専門性も必要でしょう。
両方ともストレスを抱えやすいということになりますので、
ここで、改めて看護とは何か確認をしておくと、、
保育士に共通する部分がたくさんありますね!
保育も、
子どもや保護者にとって身近な存在で、基盤となる家族の生活に関心を寄せ、それぞれの子どもに合わせて保育をするという☺
また、
患者個人だけを看護しても、周りが看護に不足していたら、それは不十分な状態と考えるんですね。
保育も、子どもに対してのみ良い保育をしたとしても、家族が、地域社会が保育の視点に欠けていたら、子どもは不利益を受けることになりますもんね。
違うのはというと、、
目的を達成するための体制は、全然違うなって😨
〈今すぐ保育士配置基準を改正しないといけない理由とは?! →リンク〉
保育所は、看護体制と違って、メインも補助もなにも、最低基準がワンオペですから。
自治体や個々の運営者の努力に頼っている状況です!
保育所以外の保育系の施設も大差はなくて、基準は酷いものです。
〈保育士の労働環境の実態って?!〉

あまり比較するのもどうかと思いますが、お給料はというと、
違いがあるのは当然としても、差があまりにもあるような気がしますね。
昔、ある保護者の方から『先生みたいな人(酷い待遇でも働きたいと思う人)が居るから、私たちが助かっているんです!』って言われたことがありますが、苦笑いするしかないですよね。
まとめ
最後にまとめです。
病気で繰り返し入院した経験から感じたことをみなさんと一緒に共有出来たらと思い書いてみました。
ここ十数年、入退院を繰り返しつつ保育の仕事をしてきましたが、今回の入院は過去の経験とは大きく異なりました。特に感じたのは、看護の現場の変化です。
以前の入院では、看護師が多く、日常的な世話もすべて行っていました。しかし、今回の入院では、業者が食事の配膳やお茶の配布、衛生管理などを担当するようになっていました。これにより、看護師と患者の触れ合いが減り、病状を細かく把握する機会が少なくなっていると感じました。
業務の合理化は、看護師の負担軽減やコスト削減には寄与するかもしれませんが、患者にとっては不安や孤独感を増す結果となっているように感じます。看護師と雑談することで不安が和らいでいたことを考えると、今回の業務分担は大事なものを失っているように思えました。
保育業界も同様に厳しい環境で働いている保育士がたくさん居ます!
無理をせずに自分の健康を優先してください!
体が資本ですので、無理を重ねると後で大きな後悔につながります。
看護師と保育士は、どちらも感情労働であり、患者や子ども、保護者にとって身近な存在です。両者ともに精神的なケアが重要であり、自分自身の健康管理も大切です。
今回の経験から、合理化だけでなく、保育を受ける子どもたちにとっても、何が本当に大切かを考える必要があると感じました。
〈保育の目的って何だろう?〉

皆さんも、自分の健康と周りの大事な人々のことを大切にしてくださいね。
それでは、また次回のブログでお会いしましょう!
最後まで、【保育のねらい(保育士の健康)】最近入院して、感じたこと 保育と看護の共通点などをお読みいただき、誠にありがとうございました。
もしご意見ご感想などございましたら、コメントで頂けますと、とても嬉しい限りです!
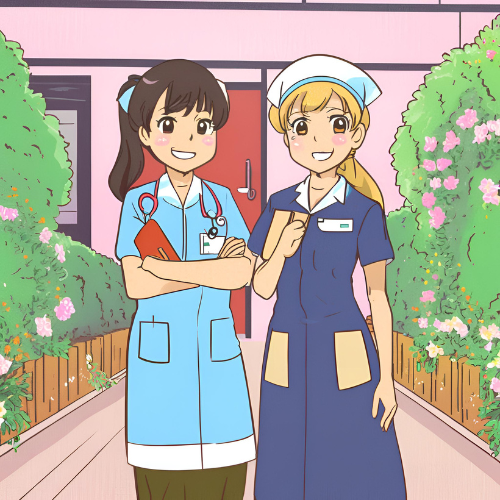


ご意見・ご感想など 子どものみかたブログ読者の方から頂きましたご意見などです。