こんにちは。いつも「子どものみかたブログ」をお読みいただき、ありがとうございます☺
よく子どもに「お友達と仲良くしようね」と教えるときに、
「自分がされて嫌なことは、相手にもしない!」
と伝えることがありますよね。
でも…この言葉、はたして本当に有効なのでしょうか?
私は最初にこの言葉を他の支援者から聞いたとき、なんとなくモヤモヤした気持ちになりました。
でもその時は、なぜモヤモヤするのかははっきりわからず…。
長く保育の仕事をして、少しずつその理由が見えてきたんです。
幼児はまだ「相手の気持ち」を想像するのが難しい時期
例えば、4歳くらいまでの子どもは、まだ自己中心性が強く、
「世界には自分だけ!」
と思っていたり、
「他の人にも自分と同じように気持ちがある」ということになかなか気づけません。
この段階では、自分の気持ちを相手に当てはめることは、ほぼ不可能ではないでしょうか。
例えば、叩かれたり、押されたり、邪魔されたりするのは、この頃は誰もが嫌かもしれません。
だからといって「相手も同じように嫌と感じているんだ」ということまでは想像するのが難しかったり。
だから間に大人が入り、
「◯◯ちゃんは嫌なんだって」
と代わりに繰り返し伝えてあげる必要があります。
それでも最初は意味がわからないことが多いでしょう。
わかったようにみえて、大人にヤイヤイ言われて怒られるのが嫌だからやめている…のかも?!
5歳ごろになると…
5歳くらいになると物事の違いに気付き始め、好きなこと・嫌いなことがはっきりしてきます。
ただし、その「嫌」や「好き」は人によって違ってきます。
たとえば「叩く」ひとつ取っても、以前は思い通りいかず、怒って叩いていた子が、
今度はふざけて「遊びとして」で叩くことがあります。
格闘ごっこや闘いごっこが好きで、仲間意識から相手もノリノリの場合もあります。
でもまだ力加減が難しく、エスカレートしてケンカになることも…。
そんな時の支援は、大人が「今のは10くらいの力だね」「100はやりすぎ」など、
数字や手の幅などの“目に見える形”で教えるとわかりやすいことがあります。
「好き・嫌い」は人によって違う
年長さん以上になると、「自分がされて嫌なこと」が相手とは違ってくることが増えます。
にもかかわらず、
「自分がされて嫌なことは相手にもしない」
をそのまま守ろうとすると、ズレが生まれます。
それがさらに進むと逆に、
「自分が好きなことなら、相手にしてもいいんでしょ?」
と考える子も出てきます。
これだと、相手が困ることも多いんですよね。
(闘いごっこが苦手な子もいますし…)
本当に伝えたいのは「気持ちは人によって違う」
私が大事にしたいのは、
「好き・嫌いの感覚は、人によって違いや差がある」
「相手がどう感じているか、わからないときは確認したり、聞いてみる」
「嫌と言われたらやめる」
ということです。
実はそれが、私のモヤモヤの正体でした。
※なお、発達の特性などで相手の気持ちを想像することが特に難しい場合は、場面ごとにルール化してパターンとして行動出来るように支援することが有効な場合があります。
このたびは「自分がされて嫌なことは相手にもしない」というテーマの記事をお読みいただき、誠にありがとうございました。
日々の保育や子育ての中で、つい口にしてしまう言葉も、子どもの発達段階や気持ちの理解によって、意味が変わってくることがあります。
今回の記事が、子どもとの関わり方を少し見直すきっかけになれば、とても嬉しく思います。
これからも、子どもの気持ちに寄り添った記事をお届けしてまいりますので、引き続き「子どものみかたブログ」をよろしくお願いいたします☺
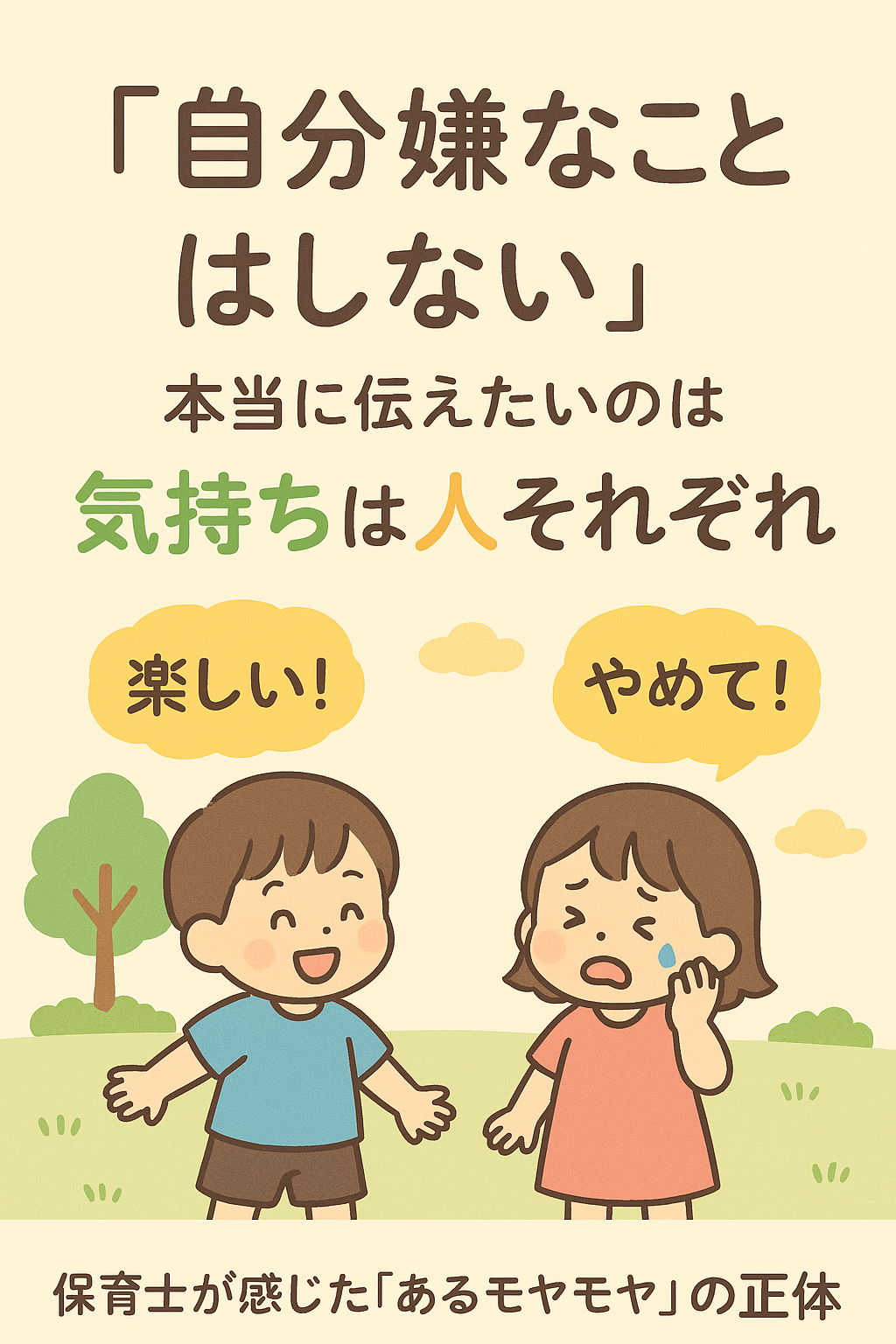

ご意見・ご感想など 子どものみかたブログ読者の方から頂きましたご意見などです。